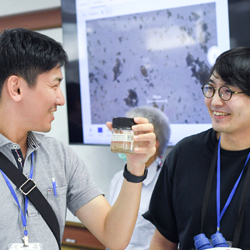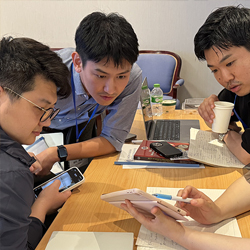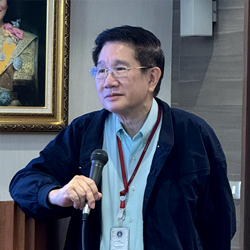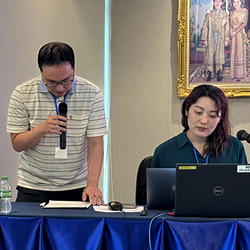【2025/2/17】消化管寄生虫症、ワークショップ
バンコクでは平均気温34℃の晴天の下、マヒドン大学熱帯医学短期研修(Onsite Short Course for Clinical and Laboratory Highlights in Tropical Medicine 2024)が始まりました。本コースは8回目の開催になります。日本ではみることができない熱帯感染症を学ぶために、熱帯医療に興味を持つ医師23名が本研修に参加してくれました。本研修はマヒドン大学熱帯医学部のDepartment of Clinical Tropical MedicineおよびDepartment of Protozoologyの協力の下、多数の熱帯医療の専門家が講師として参加しています。日本側の事務局はNPO法人グローカルメディカルサポートが担当しており森博威医師、石岡春彦医師、羽田野義郎医師、伊東直哉医師、武藤義和医師が参加しています。
第1日目は朝8:30から、医学部長Assoc Prof. Weerapongのオープニングスピーチにより開幕しました。その後、森先生によるオリエンテーションで、研修の目的やルールに加え、タイにおける生活方法、ワイ(挨拶)の仕方などのお話がされ、参加者も6つのグループに分かれました。グループでの自己紹介を通して、緊張がほぐれ、お互い楽しく打ち解けることができました。
午前の授業は消化管寄生虫の授業と実習です。前半は森先生による寄生虫の卵の形状や特徴の講義を受け、後半では実際に患者さんの便検体を自分で染めて、自分で顕微鏡を見て、寄生虫の卵を探し出してもらいました。顕微鏡実習にはAssoc Prof. Dorn, Assoc Prof. Aongartを始め、マヒドン大学の寄生虫講座のスタッフに多くサポート頂きました。みんな初めて染める便検体に興味津々、学生時代に戻ったように顕微鏡を見ながら、卵っぽいものが見つかるたびに指導教官を呼んで「これって卵ですか?」、「いや、これは違うね」とか「これは珍しいね」と言われながら学習しました。Ascaris, hookworm, Trichuris, Entamoeba, giardia等の頻度が高い寄生虫に加えてParagonimusやEchinostomaも見つけました。
お昼は病院が用意してくれたビュッフェ形式の食事。みんな初めて食べる食べ物ばかりで、辛いトムヤンクンからパッタイ、マンゴーまでいろいろなものを食べて談笑していました。
一日目の最後は森先生および日本人スタッフによる振り返りを行いました。現代のタイのマラリアの疫学と撲滅に向けての活動の歴史などのお話があり、会場の先生方もタイの医療制度などについて熱心に質問を投げかけており、あっという間の1日目が終了しました。
1日目の授業が終わったらウェルカムパーティとして、マヒドン大学周辺のタイ料理のお店へ皆で行きました。タイ料理は辛いものが多いですが、皆さん美味しい美味しいと満足気に食べながら活発な情報交換をして楽しみました。おすすめはカオニャオ・マムアンというデザートで、マンゴーともち米に練乳をかけるというものです。大変美味しいためぜひともご賞味ください。
【2025/2/18】デング熱、メリオイドーシス、トラベルメディスン
2日目が始まりました。タイの朝は早く、早朝から多くの人が電車や車に乗ってバンコクの街を行き交っております。そんな中、研修も朝8時から開始するため皆さん眠そうな目をこすりながらご参加頂きました。
朝一番は伊東先生のデング熱に関する講義です。日本でも2014年の代々木公園のアウトブレイクがあったのでみなさんも馴染みがあって記憶に新しい病気だと思います。デング熱はどのような蚊が感染を起こすのか、感染するとどういう症状が出るのか、重症化するwarning ssignとはなにかなど、病態の講義をしてもらえました。続いて羽田野先生によるメリオイドースの講義です。メリオイドーシスとはBurkholderia pseudomalleiによる感染症です。東南アジアでも特にタイの東北部やインドネシア北部の農村地域で発生する病気であり、commonな疾患の一つです。2つの疾患の講義を聞いたあとで、早速病棟ラウンドに行きます。
病棟ラウンドでは、参加者を3グループに分けて、3例の実際の患者さんにお会いして、問診と診察をしながら鑑別疾患をディスカッションしました。患者さんはタイ語で話されますが、マヒドン大学の先生に英語で通訳してもらいながら行います。今年のケースはサラセミアのあるタイ人男性の遷延する発熱、ムーガタというタイの伝統的な料理を食べたあとに発生した髄膜炎の女性、北海道旅行をしたあとに発熱をきたしたタイ人男性という経過の方々です。そのグループごとに3日目にディスカッションを行い、4日に発表、議論を予定しています。果たして診断にたどり着けるのでしょうか。議論、アウトプットを通じて東南アジアでの発熱患者へのアプローチを実践的に学びます。病棟ラウンド後はデング熱のケースディスカッション。こちらも実際の患者さんに話を聞き、患者さんのデータを見ながらディスカッションを行います。デング熱と診断されたものの発熱がない免疫不全の患者さんや、最重症なデング熱の症例の経過など、興味深いケースを学びました。
今日のお昼ごはんはタイの卵焼きとキノコ炒めとグリーンカレーです。初日のトムヤンクンは辛かったですが2日目は辛いものが少なくて食べやすい日でした。
さて、2月のタイは乾季なのであまり雨はふらないのですが、今日は朝から大雨。でもタイの雨は大雨になった後にカラッと晴れるため、午後から天気も良くなっています。午後の授業はWironrong先生によるメリオイドーシスから始まりました。午前はアウトラインの話でしたが午後は疾患の疫学や症状、治療などを中心に講義をしてもらいます。メリオイドーシスはタイのUbon ratchathani地方における菌血症で最も頻度の高い菌であり、風土病として有名な感染症です。重症のメリオイドーシスや再発例などの症例を検討しながらレクチャーを頂きました。
2日目の最後はトラベルメディスン外来。まずはPhimphan先生による講義では、渡航先でどのようなリスクが有るのか、渡航内容や患者背景によりどのような感染症のリスクが高いか、そしてワクチンを打つべきかなどのお話をしてもらい、実際にマヒドン大学のトラベルクリニックに行きました。トラベルクリニックでは、3グループにわかれて、渡航前相談の外来を実際に医師と患者役に分かれてロールプレイをしたり、黄熱などのワクチンの保管方法や接種フローの実際をみたり、渡航者の皮疹を見た時にどのような疾患を想定するかを勉強しました。渡航者診療は日本ではまだまだ少ない領域でありますが、マヒドン大学渡航者クリニックでは約100人/日の受診があります。渡航医学はDiploma in Tropical Medicine & Hygieneのコースの中に入っている他、渡航医学の修士のコースもあります。
後は森先生によるまとめの講義。帰国後の発熱患者を診察したときのアプローチについて総論をしていただきました。そして参加者たちによる質問タイムでは、今日の学習した内容で気になることを日本人講師の先生方にいっぱいぶつけて、納得行くまで議論しました。
振り返りではデング熱、メリオイドーシスを中心に振り返りました。様々な質問がでて活発に議論を行いました。
【2025/2/19】マラリア、皮膚疾患
今朝は曇天だけど気温は27℃で快適です。タイのような地域は雨が降るのは大体早朝と昼下がりだけ一気に降るので、学校や職場に行く時間と帰る時間は晴れてることが多いです。
3日目の朝は石岡先生によるマラリアの治療に関する講義から開始しました。最近のマラリアはどんどんeliminateされていく方向になりそうでありさらなる進展が期待されます。重症、耐性マラリア、妊婦症例の対応についても学びました。
次はDr.Prakaykaew, Dr.Udomsak, Dr.Tanayaによるケースディスカッションです。。実際の症例の情報を紹介しながら検査や診断、治療をディスカッションしていきます。参加者の先生たちも経験したことない病気だから、どこから考えていいのかが難しいけれど頑張ってくれました。今年の症例は低栄養、肺病変がある小児の症例、下痢の日本人男性、顔面浮腫の中年女性を議論しました。普段日本では経験できない寄生虫疾患等の診断、治療について症例を通して学びました。その後はDr.Polrat, Dr.Prakaykaew, Dr.Noppadon, Dr.Santによるマラリアのケースディスカッション。熱帯熱マラリアとリケッチアの併発例と、ミャンマーの妊婦の三日熱マラリア例、バンコクのサルマラリア例を紹介しながらフロアの参加者たちを巻き込んでインタラクティブに講義が行われました。
お昼ごはんはタイの揚げ物が中心です。マヨネーズも甘い味がして変わったものを食べれるいい機会です。フルーツもローズアップルとパパイヤを唐辛子入りの砂糖につけて食べます。
午後になると毎年恒例“皮膚科の名探偵”の講義。タイで経験する皮膚科領域の感染症疾患について学びます。Pityriasis(バラ色粃糠疹)やmolluscum(伝染性軟属腫)、Paederus dermatitis(ハネカクシ皮膚炎)などの日本語ならわかる疾患も英語で表現されると知らない単語だらけですが、その場で翻訳しながら皮膚病変の特徴をたくさんの写真や動画とともに学びます。感染症での皮疹は真菌、ウイルス、細菌、寄生虫、昆虫など多岐にわたり、それぞれが特徴的なので、こういった機会にみることができればきっと日常臨床でも鑑別に挙げられると思います。
午後の後半は、初日に病棟ラウンドをした時に見た患者さんの発表の準備です。最終日に各グループが症例紹介と経過の報告、そして鑑別をあげながら診断検査の方針をプレゼンするため、話し合いました。時間が過ぎても鑑別、治療方針について議論を続けました。
最後は森先生による一日の振り返り会があり、タイの医療制度や最終日のハンセン病の話などをして終了しました。
【2025/2/20】ハンセン病病院訪問、症例検討
最終日の朝は参加者全員でleprosy(ハンセン病)の病院 Raj Pracha Samasai Instituteへ向かいます。Leprosyはタイでは多くの患者さんがありましたが、今では年間100例を切るまでに減少しており、数年前には患者減少のため、leprosyの病院を一般病院として開放し、単独施設ではなくなっております。到着するとまずは病院の先生と検査技師さんの講義を聞きます。タイでは皮膚科の医師はかならずleprosyの病院を実習するというルールが有るため、基本的には常に鑑別に挙がる病気のことでしたが、日本では実際にleprosyをみることはまずないため、特徴的な皮疹を見ても鑑別に挙がることはまずないのではないでしょうか。様々な皮診のパターン、神経診察、Slit skin smear、治療方法について詳細に学びました。活発が議論を行いました。実際にleprosyの患者さんにも来ていただき、特徴的な皮疹の診察、神経の肥厚、治療の現実などを見させてもらい、またとない経験ができたと思います。特に尺骨神経の肥厚の神経診察を経験しました。慢性期のハンセン病は四肢の拘縮や変形を伴なうため装具の作成、リハビリが重要です。ハンセン病病院では専任の装具製作者が常勤しており患者の体型に合わせて専用の装具の制作が可能です。装具の制作についても詳しく学びました。
leprosyの病院ではおやつとしてサンドイッチと餅のお菓子を頂きました。どの病院もこういったホスピタリティがあるのがタイの良いところです。
午後になり、最後のセッション。2日目に診察に行った病棟の患者さんの診断プロセスや鑑別とマネージメントについて、各グループで発表を行います。症例報告の形でおこない、疾患を導き出します。熱帯医療領域の急性発熱性疾患(AFI: Acute febrile illness)の考え方を学ぶというのが目標です。マヒドン大学から多くの講師が参加してくれました。Dr.Prakaykaew, Dr.Viravarn, Dr.Chayasin, Dr.Wironrong, Dr.Sant, Dr.Tanaya。それぞれの症例報告に対して議論を行います。馴染みが薄い熱帯病も鑑別に挙げながらcommonな疾患も同時に考えていきます。メリオイドーシスやデング、マラリアといった診断の遅れは致命的になるような疾患のサインを見逃さないということもこの発表の醍醐味です。場所が変わり疾患の疫学が変わると鑑別疾患が異なります。熱帯地域での発熱のアプローチを基本から学ぶ良い機会となりました。 議論はヒートアップし、タイ側からも日本側からも多くの質問、意見が出て実りあるディスカッションができました。
3グループも無事に発表が終わり、Dr. Watcharapongによる総括とcertificateの授与式が行われ、最後は森先生による総合まとめで今年の熱帯医療短期研修は終了いたしました。参加者の先生たちは会の終了後もずっと仲良くお話をしており、ここでの出会いや新しい発見を日本に持ち帰って、拡げていってくれるのではないかと期待しています。
ご参加ありがとうございました!また来年、同じように熱帯医療を勉強したい先生たちと熱帯医学研修でお会いできることを楽しみにしています。